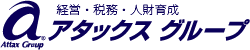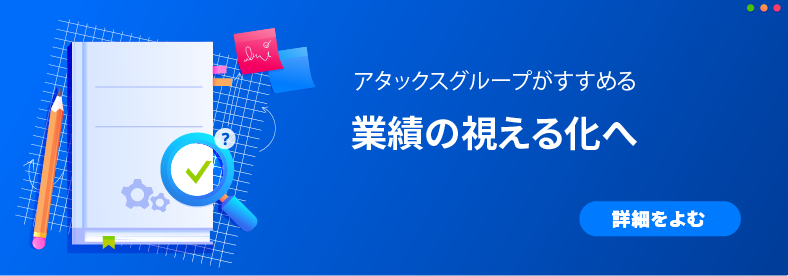インフレと金利上昇が企業収益に与える影響
近年、インフレと金利上昇が同時に進行しています。消費物価や原材料価格の高騰により、企業のコスト構造は一段と厳しさを増しています。
また、金利の上昇は資金調達コストの上昇を招きます。この「ダブルパンチ」によって、資金繰りが悪化する企業が増加しています。
特に中小企業にとっては、利益を確保するだけでなく、資金繰りの巧拙が経営を左右する時代となりつつあります。
多くの企業では、価格転嫁が最重要課題として取り組まれていますが、こうした環境下で見落とされがちな重要な経営指標があります。
それが「CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)」です。
CCCとは何か?
CCCとは「現金化までに要する日数(キャッシュ回収サイクル)」を示す経営指標です。つまり、企業が在庫を仕入れ、販売し、その売上代金を回収するまでにかかる日数を指します。
この期間が長ければ長いほど、資金は企業内部に滞留し、運転資金が逼迫します。場合によっては、外部からの借入でその不足資金を補う必要も出てきます。
一方で、CCCが短い企業は、効率よく資金を回転させていると言えます。
CCCは以下の3つの回転日数の要素で構成されます。
①売上債権回転日数
商品を販売してから代金を回収するまでの日数
②棚卸資産回転日数
商品を仕入れてから販売するまでの日数
③仕入債務回転日数
商品を仕入れてから仕入先へ代金を支払うまでの日数
これらを用いたCCCの算出式は下記のとおりです。
= 売上債権回転日数 + 棚卸資産回転日数 - 仕入債務回転日数
*1:必要に応じて、分母を売上高の代わりに売上原価で代用しても差し支えありません。
なぜCCCに注目すべきなのか?

注目すべき背景は主に以下の2点です。
②金利上昇による「支払利息の増加」
ここでは、具体的な数値例を用いて見ていきましょう。
Before:インフレ前
年間売上高が20億円の場合、
必要運転資金 = 20億円 ×(73日 ÷ 365日)= 約4億円
仮に金利を2%とすれば、
支払利息 = 4億円 × 2% = 約800万円
ここから、インフレ後のケースを2つ想定します。
After①:仕入・在庫・売価が1.3倍に上昇し、価格転嫁が実現されている場合
年間売上高 = 20億円 × 1.3 = 26億円
必要運転資金 = 26億円 ×(73日 ÷ 365日)≒ 5.2億円
金利が2%から2.3%に上昇したとすると、
支払利息(想定金利2.3%) = 5.2億 × 2.3% ≒ 約1,200万円
価格転嫁に成功し利益率は維持できているものの、滞留資金が1.2億円増加し、資金繰りが圧迫されています。
加えて、金利上昇で支払利息も増加し、収益をさらに圧迫します。
After②:価格転嫁が不十分で売価は1.1倍にとどまっている場合
CCC ≒ 43日(売上債権)+ 71日(棚卸資産)- 35日(仕入債務) = 79日
年間売上高 = 20億 × 1.1 = 22億円
必要運転資金 ≒ 22億円 ×(79日 ÷ 365日)≒ 4.8億円
支払利息(想定金利2.3%)= 4.8億 × 2.3% ≒ 約1,100万円
このように、価格転嫁が不十分で利益が減少している中でも、滞留資金および金利負担は拡大しており、経営に二重の打撃を与えています。
つまり、After②のようにCCCが悪化している場合はもちろん、After①のように同じ「CCC73日」でも、インフレ環境下では経営への影響が格段に大きくなっており、CCCを改善・短縮することの重要性が高まっていると言えます。
CCCを改善するための対応策
では、実際にCCCを短縮するためにはどのような対応策が必要でしょうか?
以下に、CCCを構成する各要素について対応策を示します。
①売上債権回転日数の短縮
・回収条件の見直し(支払サイト短縮交渉)
・入金遅延への対応強化
・滞留債権の管理・早期回収の徹底
・与信管理の厳格化
・早期回収割引やファクタリングの活用
②棚卸資産回転日数の短縮
・需要予測の精度向上
・発注点管理の徹底
・サプライチェーン見直しによる調達リードタイム短縮
・社内業務プロセス見直しによる製品化リードタイム短縮
・滞留・余剰在庫への対応ガイドライン整備
(在庫保管場所の整理整頓、評価見直し、処分セール、廃棄等)
③仕入債務回転日数の延長
・支払条件の再交渉(支払サイト延長)
・リバースファクタリングの導入検討
特に②の棚卸資産回転日数の短縮は、企業内部のオペレーションの見直しで改善できる要素が多く、在庫を多く持つ事業体にとっては優先的に取り組むべき施策と言えます。
まとめ

成長戦略や価格転嫁、生産性向上といった利益最大化の取り組みと同様に、キャッシュフロー管理は経営においてますます重要なテーマになっています。
インフレと金利上昇が続く中、資金調達は今後ますます厳しくなる可能性があります。そのような環境において、CCCの管理は企業の健全経営を左右するカギを握ります。
「いかに効率よく現金を生み出すサイクルを構築できるか」
まずは、自社のCCCを計算し、現状を把握するところから始めてみてはいかがでしょうか。
筆者紹介

- 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長 中小企業診断士 平井 啓介
- 会計を中心とした業務系システムを扱う大手システムベンダーを経て、アタックスに参画。システムエンジニア時代は、会計システムを中心に、中堅中小企業~上場企業まで業種を問わず、約60社の業務改革を支援。経営課題から逆算したシステム企画、徹底した業務プロセスの掌握・分析を得意とし、システム企画~導入・運用支援までの総合的なプロジェクトマネジメントを推進。アタックス参画後は、システムエンジニア時代に得たファシリテーションスキル、多業種に渡る業務知識を応用し、経営計画策定サポート、業務プロセス改革サポート(BPR)、PMIサポート(M&A後の経営統合支援)、M&Aサポートに従事。近年は、中堅中小企業流のデータサイエンス(経営可視化)によるDX支援にも注力している。特に「計画策定」「各種制度構築」後の現場に入り込んだ「実行推進支援」に強みを持つ。