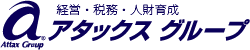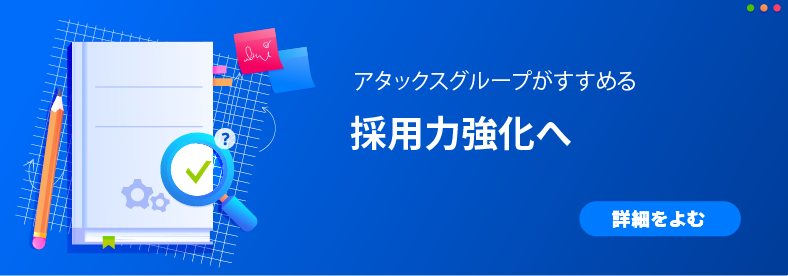キャリタス就活など新卒向けの就職支援サイトを運営する株式会社キャリタスが、2025年卒採用内定動向調査を公表し、以下のことを示しました。
内定者充足率(採用計画に対する内定者の割合)
65.6% (前年同時期の 67.9% をやや下回る結果)従業員規模が小さい企業ほど充足率が低い傾向
大手企業:75.6%
中小企業:57.2%
読者のなかにも、新卒採用で苦戦されているという方がいらっしゃるかもしれません。
面接や内定出しのタイミングは早期化している一方、思うように内定者を確保できないため採用活動を終了できず、 採用活動が「早期化」と同時に「長期化」している、そんな企業様からのご相談をいただくことが少なくありません。
こうした企業側にとって厳しい採用戦線のなか、見事に採用に成功した、ある会社の実例をご紹介します。
採用成功の秘訣は「カッコつけるのをやめた」
自動車部品メーカーである中堅企業N社の実例です。N社は、2025年卒から採用活動を抜本的に変えました。
結果、前年は年明けにようやく新卒者2名を確保できた状態であったのに対し、今年は9月までに6名から内定承諾を得ることができました。しかも最終面接で不採用者を数名出したうえでの結果です。
採用数だけではありません。採用した人材のレベルも飛躍的にアップし、初めて、県外の有名大学の学生を採用することができました。
量においても質においても、劇的に結果が変わったといえます。この要因について、同社社長は次のように語ります。
「カッコつけるのをやめました」と。
それまでは、いわゆる「カッコよく見せよう」と無意識に採用活動をしていました。しかし、思い切って同社は最寄り駅の改札内にコピー広告を掲出しました。
そのコピーは、「フォロワー6人しかいません」。 X(旧ツイッター)の当時のフォロワー数を、いわゆる自虐的に表現したのです。
社長自身は「本当は恥ずかしくて嫌だ」という気持ちだったそうです。
創業75年、今や業界内では知名度が高い会社であり、3代目社長にとってはこれは正直な思いでしょう。しかし、思い切って実施しました。
会社の”ありのまま”を伝える姿勢が大切

昨今、就職活動において口コミサイトの情報を参考にする学生は非常に多くなっています。
株式会社インタツアーが行った調査によると、就活中に「口コミサイトを利用したことがある」と答えた人は93.5%を超えており、就活学生にとって口コミサイトが欠かせないツールとなっていることがうかがえます。
筆者自身も、「企業側の情報はすべて疑ってかかっている」という学生の声を直接聞くことがしばしばあります。
1990年代後半に生まれた、いわゆるZ世代の多くは生まれたときから情報があふれる環境で育ち、真偽不明の情報が日常的に行き交うのを目の当たりにしています。
ですから、「この情報は本当か」「誇張されていないか」「嘘ではないか」と常に疑っているといえます。
企業側の想像以上に、彼らの”見抜く力”は高いと考えたほうがよいでしょう。
「カッコつけるのをやめました」この社長の言葉は、そうした背景を踏まえると非常に意味があると筆者は考えるのです。
なお、行ったのは最寄り駅のコピー広告だけではありません。同社社長は面接に来た学生に対して「嘘をついても仕方がないので、最初に伝えさせてください」と次のように説明しています。
約800度の炉が7台もあり、夏はとても暑い環境です。
(湿気を逃がすアイスベストの支給や手当などの対策は行っています。冬は暖かいので快適です。)
■機械加工工場の環境について
製品についた水や切り粉を吹き飛ばすため、エアブローの音がうるさいです。
(騒音を減らす対策に取り組んでいます。)
■事務所作業の環境について
デジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいるとは言えません。
経理クラウドソフトや人事クラウド管理ソフト、生産管理システム、購入品管理発注ソフトなどを急ピッチで整備しているところです。
■口コミサイト上に載っている不満の声について
過去の退職者の不満が口コミサイトに残っています。
(私は毎日工場を巡回していますので、気になることはそのタイミングで相談してもらいたいです。対策を講じて、気持ちよく働ける職場にしたいと考えています。)
ここまで、会社内部の”ありのまま”を伝えることに、躊躇する読者の方は少なくないと思います。
しかし、同社の結果はその”躊躇”を”勇気”に変えるかもしれません。なぜなら、この社長面接に参加した学生11名に内定を出し、うち6名が承諾したからです。
内定を出しても一名からも承諾を得られないという中堅・中小企業もあるなか、これは見事な成果といえます。
包み隠さず伝える姿勢こそが信頼感を高めるのでしょう。もちろん、”ありのまま”を伝えるには勇気が要りますが、入社後に「思っていたのと違う」と言われて辞められるのは避けたいことです。
まとめ

一人の人生を良くも悪くも変えるのが、企業がおこなう採用活動です。
筆者は、企業側の責任としてありのままを伝えることを推奨しています。それができない企業はこれからの時代に安定して採用し続けることは難しいでしょう。
今こそ”嫌われる勇気”を持つべきです。そうすることで、いっときの印象は悪くなるかもしれませんが、入社後に「イメージどおりだった」と感じてもらえます。
企業は入社前と入社後のギャップ、いわゆるリアリティショックを与えないよう、採用活動のなかで、意識して情報提供しなければなりません。
N社の実例は、その重要性を教えてくれます。
ここまでお読みいただいた方にはぜひ、そのことを自社の採用活動を変えるヒントとして捉え、具体的な行動に繋げていただきたいと思います。
なお、N社が採用を改善するきっかけとなったのは、筆者のセミナーに参加したことでした。
危機感を持っている会社の行動スピードは速く、同社社長は講義受講から1週間で採用戦略を抜本的に立て直し、筆者に相談してくださいました。
その後、採用担当者(総務兼務)が中心となり、採用プロジェクトチームを立ち上げ、約1か月弱で採用活動を本格的にリスタートしたのです。
「このままではまずい」そんな危機感をお持ちであれば、次は貴社の番かもしれません。どうか勇気を持って、一歩を踏み出してみてください。
無料相談会も随時行っています。こちらからお気軽にお問い合わせください。
筆者紹介

- 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 取締役 酒井利昌
- 学習塾業界、人材サービス業界を経て、アタックスに入社。採用と教育支援の両軸で、年間200日以上、現場指導に従事。採用コンサルティングにおいては、営業・マーケティングノウハウを転用した独自メソッドを用い、携わった企業すべてを短期間で目標達成に導いている。著書に「いい人財が集まる会社の採用の思考法」(フォレスト出版)があり、2019年8月発刊以降、ロングセラーを記録している。2023年10月には増補改訂版も刊行し、ベストセラーとなっている。