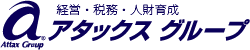企業は環境適応業である、といわれますが、環境適応にはイノベーションが有効です。
イノベーティブな組織であれば、魅力的な商品開発ができたり、新たな生産方式で製造コストを低減できたりと、環境変化に適応し、売上や利益を拡大することが可能になるからです。
それどころか、変化を先読みし、変化を創造することさえできます。
組織がイノベーティブでなくなった時、企業のダイナミズムが失われ、衰退への道を歩み始めるのかもしれません。
セブンイレブン(以下、セブン)が苦戦している要因は?
セブンイレブン(以下、セブン)が苦戦しているようです。最近の各種メディアでも、セブンの苦戦を伝える記事が増えています。
セブンの社史が編纂された2004年当時は、セブンが他社を大きくリードしていました。2004年の全日平均日販は、セブンが650千円、他社が470千円で1.38倍の差がありました。
しかし、2023年はセブンが691千円、他社が559千円で1.23倍に差が縮まっています。伸び率ではセブンが6%、他社が19%です。
かつてのセブンは、存在そのものがイノベーティブでした。
コンビニという業態の新規性、顧客の立場で考える店舗づくりや商品開発、ドミナントを重視した出店戦略など、セブンが実現することで一般的になった概念が多くありました。
しかし、最近の商品開発などの打ち手を見ると、セブン発というものは見られなくなっているように思います。
セブン絶好調時に編纂された社史の題名は、「セブン-イレブン・ジャパン 終りなきイノベーション」です。
セブンが苦戦する要因は様々あると思いますが、中でもイノベーションが失われつつあるというのが大きな要因ではないかと思います。
では、イノベーティブであるにはどうしたらよいのでしょうか?
イノベーションと新たな価値創造
イノベーションというと、シュンペーターの新結合を思い浮かべる方は多いと思います。
新結合とは、既存の知を組み合わせることで新たな価値を創造すること、と説明される概念です。
シュンペーター自身はイノベーションという言葉を使っていないようですが、この概念を持って、イノベーションといえばシュンペーターとイメージが定着しています。
新結合による新しい価値の創造は、多くの事例があります。
例えば、回転寿司。回転寿司の生みの親とされる故白石義明氏は、大阪の立ち喰い寿司店経営者だった頃、視察会でビール工場を訪問した際、ビール製造のベルトコンベアにヒントを得て、多数の客の注文を低コストで、効率的に捌くことを目的とした回転寿司を開発したそうです。
そうして、世界最初の回転寿司店「元祖廻る元禄寿司」を開店しました。
生産方法では、カンバン方式。1960年代、アメリカ視察に参加していたトヨタ自動車の一行が、ふと立ち寄ったスーパーマーケットで「商品棚に空きができたら商品を補充する」というやり方を見てヒントを得たといわれています。
それまでの前工程で作って後工程に流すというやり方から、後工程から前工程に情報(売れた分)を流して生産する方法への切り替えです。
回転寿司、ベルトコンベア、自動車生産、スーパーマーケットと、登場するものは新しいものではありませんが(既存の知)、それぞれが結合することで(新結合)、画期的な価値が創造されています。
上述の事例では、視察会への参加がきっかけとなったように、イノベーションを推進するには自分は知らない「既存の知」を探索する必要があります。
既存の知を結合するためには、
の2つがありますがいずれも、「多様な知」を持ち寄って新結合を図るということです。
多様性つまりダイバーシティーを経営に取り入れる経済的な動機はここにあります。
組織にプラスの効果があるダイバーシティーとは?
ダイバーシティーは大きく二つに分類されます。一つは、人と人のダイバーシティー、もう一つは自己内のダイバーシティーです。
前者はさらに、デモクラフィー型とタスク型に分類されます。デモクラフィー型は、性別、人種、年齢などにおいて多様な人が集まるもので、一般的にいわれるダイバーシティーのイメージです。
タスク型は、外見には現れにくいもので、知見・能力・経験・価値観などにおいて多様な人が集まるものです。
最近の経営学の実証研究では、
とされています。
実証研究ではタスク型は効果があるとされていますが、中堅中小企業では多様な人材を採用して取り組むこと自体が難しいようです。
中堅中小企業のイノベーションを支えるダイバーシティーとは?

筆者は、中堅中小企業のイノベーションを支えるダイバーシティーは、自己内のダイバーシティー(イントラパーソナルダイバーシティー)が現実的かつ効果的だと考えます。
経営者だけでなく、社員一人ひとりが自己の「知の範囲」を拡大していき、多様な知を自己内に蓄積し、自己内で新結合を図るというものです。
事例でご紹介した回転寿司も、カンバン方式も視察会に参加した経営者や社員が、新たな知を吸収し、既存の知との結合を実現しています。
イントラパーソナルダイバーシティーに、それほど難しいプロセスは必要ありません。
問題意識や使命感があり、その解決や実現のために新たな知を積極的に探索する姿勢があれば、誰にでもできるプロセスです。
国内外視察会、異業種交流会、研修会への参加や、書籍、経済ニュースを活用するなど、新たな知を探索する機会は多くあると思います。
毎日、新たな知を吸収することで、日々イントラパーソナルダイバーシティーを拡大し、イノベーティブな社風を作り、成長発展していただければと思います。
アタックスグループでは、経営者、経営幹部、社員のイントラパーソナルダイバーシティーを拡大する社長塾、次世代リーダーズ育成プログラム、経営財務コーチングなどをご用意しています。
これらサービスを通して、受講者の「知の範囲」を拡大するための情報や事例などを提供し、人と組織のイノベーションを支援しています。
ご関心のある方はこちらからお気軽にお問い合わせください。
筆者紹介

- 株式会社アタックス クラフトパーソンズ・センター 主席コンサルタント 諸戸 和晃
- 教育のスペシャリストとして財務研修コンサルで活躍。担当分野は、財務研修講師、財務コーチング、役員会指導、経営顧問、中国子会社管理。研修以外では主に、月次決算制度や原価計算制度、キャッシュフロー管理制度などの経営管理制度の構築や、未来決算書(数値シミュレーション)を使った経営計画策定支援に従事。月次決算をベースに企業の経営課題を発見・整理し、これまで多くの企業の経営のアドバイザーを務める。